「我が国の歴史を振り返る」(8) 江戸時代中期の周辺情勢
▼はじめに
前回、『先占の原則』を紹介しましたが、1988年に英国のサッチャー首相が「ヨーロッパ人がいかにこの世界の多くの土地を探検し、植民地化し、文明化したかは、まことにすばらしい勇気と才覚の物語でありました」と発言し、植民地主義に対して謝罪する必要がない旨の発言をしていたことも紹介しておきましょう。
同様に、イギリス時代の統治下にあったインドを舞台にした作品で知られる、英国の小説家・詩人のキップリング(1865 – 1936)が「自分たち西洋人は『白人の責務』を担って野蛮な民の世話を焼くために文明の事業をした」と発言したことに対して、“あまりに露骨な自己肯定だ”と批判する記事を読む機会がありました。
たしかに、最近の香港デモなどをみるに、イギリスが広めた民主主義が北京政府の権威主義より数段優れているのは明白なので、地球上の人類の歩み全般を考えると、西欧社会による植民地化を一概に全否定できない側面があることは事実なのでしょうが、長い間、有色人種に対する人種差別、そして植民地住民の迫害・搾取・殺戮が当然のように繰り返されたのです(香港デモについては、いずれ本歴史シリーズでも取り上げたいと考えています)。
▼隣国「清」の興亡
西欧列国の植民地化に触れる前に、簡単に、中国の「清」について触れておきましょう。江戸時代の始まりとほぼ同時期の1616年、女真族のヌルハチが満州を平定して清の前身である「後金国」を建国しました。そして1936年、民族名を満州族と改め、国号を「清」と改称、1644年に「明」が滅んだのを機に、首都を北京に遷都し、中国支配を始めました。
「清」は、武力をもって「明」の皇帝にとって代わるという姿勢を取らず、「明」を滅ぼした逆賊を討伐したという形をとったことに加え、科挙など「明」の制度をそのまま存続させるなど、あくまで「明」の“衣鉢を継ぐ”正当な中華帝国であることを全面に出したのでした。
異民族の満州族の支配を圧倒的多数の漢民族がなぜ受け入れたか疑問が残りますが、その理由として、中国にはもともと“天下意識”はあっても国家意識や民族意識は極めて希薄だとし、例え、外来民族であっても「真命天子」(真に天命を受けた天子)であれば、中華世界に君臨できるとの分析があります。だから、漢民族以外のモンゴル人(元)や満州人(清)が統治できたのでした。古来より、民衆は漢民族よりも異民族に新しい政治を期待したという一面があるともいわれます。
さてその後、「清」は領土を拡張し続け、1689年には、ロシアとの間に「ネルチンスク条約」を結び、両国の国境を外満州の北側、つまり黒竜江・外興安嶺(そとこうあんれい:ロシア名はスタノヴォイ山脈)に定めました。「ネルチンスク条約」は、中国が外国と対等に結んだ最初の近代的条約といわれます。ロシアにとっては、19世紀後半までこの正面の“南下”をはばまれることになりました。
「清」はまた台湾、北モンゴル、東トルキスタン、チベットに至る、現在の中国領土を超える“版図(はんと)”を持ち、18世紀に全盛時代を迎えました。
我が国にとって、(直接の脅威にならない程度の)“強い”「清」は、欧州諸国のアジア進出とロシアの“南下”防止の手段として、国防上はありがたい存在でした。しかし長くは続かず、「清」の弱体化と連動して幕末の混乱が起こります。
▼世界の85%を支配した欧州列国
市民革命や産業革命の成果を活用して近代化を果たした欧州諸国は、イギリスを筆頭にして競いながらすさまじい勢いで世界の各地を植民地化しました。
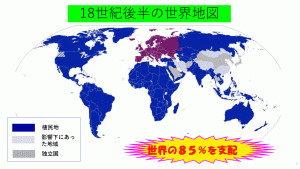
地図は、18世紀、アメリカが独立する前の世界地図です。当時、欧州列国は、産業革命によって築き上げた近代軍を遺憾なく発揮して“我が物顔”で世界の85%を支配したのです。地図からわかりますように、当時、からくも独立を維持していたのは、日本、朝鮮半島、タイ、サウジアラビア、アフガニスタン、それに中国などごく少数ですが、中国はすでに一部浸食されつつありました。
特に問題だったのは植民地支配のやり方でした。冒頭に紹介しましたように、欧州列国が支配した植民地では、有色人種を動物や獣のように扱うなど徹底した人種差別によって迫害や搾取が行われ、また、吐き気をもよおすような殺戮も繰り返されたのでした。
▼アメリカの独立・南北戦争
これまで触れました欧州諸国の「大変革」や我が国を震撼させた「ペリー来航」と時は少し前後しますが、アメリカの独立戦争や南北戦争をまとめて振り返っておきましょう。
アメリカの現在の隆盛があまりにも華々しいため、通常私達は、1492年にコロンブスがアメリカ大陸を発見し、1620年、メイフラワー号で清教徒が移民した後、1776年にアメリカが独立するまでの約150年もの間、アメリカは、イギリスをはじめ、フランス、スペインの“植民地”だった事実に忘れてしまっています。
もちろん、主にキリスト教徒の白人が移民したわけですから、他地域の植民地とはその様相が違っていたことはまちがいないと思われます。そのような中、13州の合衆国が団結して宗主国・イギリスの植民地政策に抵抗して独立に向かったのは、厳しい課税、中でもそのきっかけはすべての印刷物に印紙を貼って税を取り立てようとした「印刷法」だったといわれています。
アメリカらしく、独立当初から現在の2大政党の原型となる、共和主義を信奉して力強い国家建設を目指すグループと民主主義を推進して大きな政治的平等性を目指すグループが存在していました。
1776年の独立宣言後、イギリスが反撃に出ました。しかし、フランス、後にオランダやスペインがアメリカ側に付いて参戦した結果、イギリスは単独で戦争を行うことになりましたが、戦いは1783年まで続き、「パリ条約」でアメリカは独立を勝ち取りました。米国内には、あくまで国王に忠誠を誓う「王党派」の人々もおりましたが、イギリス敗北の後、その一部はカナダなどに移住しました。
戦いはこれで終わりませんでした。執拗なイギリスは、今度は米国内のインディアンをそそのかし再び戦いを挑みました。この戦いは、「米英戦争」(1812年~1814年)といわれています。同じ時期の欧州は「ナポレオン戦争」の真っ最中であり、イギリスは「米英戦争」に戦力を割く余裕がなかったこともあって、1814年、「ガン条約」で米英は講和し、戦争は終結しました。
この戦争で最も熾烈な戦いは、ボルチモア近郊の「マックヘンリー要塞の戦い」でした。この時の健闘を称える詩にメロディがつけられたものが、アメリカの国歌「星条旗」となっています。
かくして、完全に独立を果たしたアメリカでしたが、国内には、工業化を推進して奴隷制廃止を主張する北部と、農業中心で奴隷制存続を主張する南部の対立が残りました。南部の11州は合衆国を脱退し、「アメリカ連合国」を結成しました(アメリカに2つの国が存在した時期があったのです)。
「南北戦争」と言われるこの内戦は、1861年から1865年まで4年も続き、南北合わせて20万人を越える戦死・戦傷者を出す、すさまじい戦いとなりました。最終的には北部側が勝利し、リンカーンの有名な奴隷廃止演説に繋がったのはよく知られています。(以下次号)
