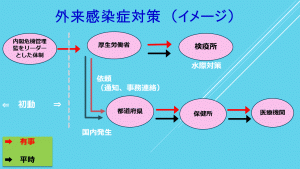我が国の危機管理体制 〈感染症対策を例にして〉
ヒトと感染症の歴史は長く、紀元前エジプト時代にさかのぼる。その時代のミイラから、脊椎カリエスに特徴的な背骨の屈曲を示すものが複数発見された。脊椎カリエスは、結核菌によっておこる骨病変であり、その当時すでに結核が人々の間に流行していたことがわかる。結核は最も人類と付き合いが長ため、病因解明、治療法の確立(化学療法、ワクチン)、予防といった、現代医学の基礎となった疾患である。結核の他、天然痘ウイルスも長い間人類を苦しめた感染症であるが、有効なワクチンの開発により、地球上から根絶された。このように、衛生状態などの改善に加え、ワクチン、薬剤の開発などにより、感染症は少なくなり、先進諸国にとって、すでに「過去の病気」と言われるようになった。
ところが、既に制圧された感染症は、新たな脅威となって私たちの前に立ちはだかるようになった。それは、HIV/AIDS、MERS, SERSといった新しい感染症の出来とともに、かつて制圧された病原体が、新たな脅威として、私たちの前に立ちはだかってきたからである。その脅威とは生物テロである。
生物テロに関する研究は世界中でなされてきた。その研究者を驚かせたのは、我が国のカルト集団、オウム真理教が行った、炭そ菌、ボツリヌス菌によるバイオテロである。オウム真理教は、「地下鉄サリン事件」を引き起こした集団として有名であるが、彼らたちが行ったこのテロは成功しなかったが、この事件に世界は驚愕した。オウム真理教は生物テロの専門家集団をもたなかった。そのような“素人”組織が、通常の集合住宅のキッチンで、生物兵器を量産していたという事実が、世界中を震撼させたのである。生物兵器は「貧者の兵器」と呼ばれるが、それを実証したのが、世界初のオウム真理教によるバイオテロである。これがきっかけとなり、世界はバイオテロを現実のものとして動き出した。WHO(世界保健機関)や欧米各国の政府機関は、バイオテロ専門部署を作った。また、WHOが”Health Security”という言葉を使いだしたのも、オウム事件がきっかけであった。この言葉が意味するものは、「健康問題はもはや、安全ではない」という事である。
こうした世界の動きに比して、当の我が国はどうだったのだろうか。オウム事件の後、H1N1豚インフルエンザ(新型インフルエンザ)、エボラ感染症、MERSなど、世界的に重要な感染症が発生したが、その対応を見る限り、大きく遅れている、と言わざるを得ない。象徴的な例が「水際作戦」である。水際作戦は軍事用語であり、その有効性は軍事的にも大きく疑問視されている。
感染症対策において水際作戦が使用されたのは、14~15世紀、世界中で猛威を振るった、ペスト流行である。当時、イタリア等の海岸線で、汚染地からの船を国内に入れないために、40日間留め置いた。検疫(Quarantine)の由来はここから来ている。結果として、ペストから逃れた国はなかったのである。また、当時の輸送機関は船が主体であったが、現在は飛行機である。48時間以内世界中のどこでも行かれ、多くのトランジットが行われている現代で、「水際」という言葉自体、時代遅れ甚だしい。H1N1豚インフルエンザ流行の際、「感染者を一人も入れるな!」のスローガンのもと、防護服に身を包んだ検疫官が空港を駆け回った姿は、我が国では英雄視されたかもしれないが、世界の失笑をかっていた。WHOは「検疫の有効性は確立されていない。海外からの渡航制限をしないよう」、こうした水際作戦を繰り広げた我が国を名指し同然で注意喚起を行ったのも、記憶に新しいところである。
なぜ、“先進国”と称される我が国が、このように世界とかけ離れた感染症対策を行うのだろうか。それは、「有事と平時の区別がついていない」すなわち、「危機という概念がない」という事に尽きる。この事実を示す一例が、検疫法と感染症法の二本立ての法律である。
感染症に対する法律としては、検疫法と感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)がある。また、緊急事態と認識された場合は、新型インフルエンザ法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)がある。これらの仕組みが、有事(緊急時)に即しているか、というと、そうではない。
まず、このような法体系に基づいた仕組は効率的ではない。検疫法は、国内に常在しない感染症が国内に入ることを防ぐための法律で、活動主体は厚生労働省の出先である検疫所である。検疫所は主要国際空港と、港という外国からの玄関口にある。ところが、一たび国内に入ると、検疫法は外れ、国内法と呼ばれる感染症法に法って、感染症対策が行われる。この時の活動主体は、地方自治体だ。2009年の新型インフルエンザ流行の際、防護服を着て空港内で活動していたのは検疫所職員で、2014年、デング熱患者発生の際、同様の防護服を着て、代々木公園などを消毒していたのは、東京都の職員だ。また、検疫所の職員は、国際線ターミナルの制限区域に立ち入ることはできるが、国内線旅客ターミナルには立ち入れない。
感染症法も国の法律であるから、厚労省の関与がないというわけではないが、感染症法に指定された感染症が発生した場合は、個人ないし医療機関が保健所に届けるというのが骨子で、その情報を地方自治体通じて国に報告するという流れである。それゆえ、厚労省は、新型インフルエンザ流行の際も、国で決定された事項を「通知」あるいは「事務連絡」という形で地方都道府県に依頼をすることになる。
1979年FEMAアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁:Federal Emergency Management Agencyレオ・ボスナー氏が来日し、1年間の視察ののち、多くの提言をおこなっている。それ等をうけて、指揮命令系統の一体化がはかられた。すなわち緊急事態と国が認識した場合は、内閣官房などが主体となった初動体制が敷かれることとなった。内閣情報調査室から総理、官房長官、危機管理審議官、ならびに、内閣危機管理監(現在は警視総監)、内閣官房副長官補(官僚)、危機管理審議官に速報が入り、官邸対策室ができる。対策室は、緊急参集チームと協議して、関係省庁尾局長級が招集され、有事の種類、事態などに応じて、主幹府省庁が決定される。エボラ出血熱に関しては、現在、内閣官房新型インフルエンザ等対策室が、先導を取ることになっている。
一見、このように統一された指揮系統の元、問題なく組織が稼働すると思われるが、残念ながら、実際の稼働となるとそうではなくなってくる可能性が高い。検疫法と、感染症法の、2つの柱があるという事は、それらの法令に伴う棲み分けがあるという事である。具体的には、厚労省本省→結核・感染症課⇔検疫業務管理室→検疫所という厚労省ルートと、保健所→地方自治体→厚労省という地方自治体主体の枠組みである。
国と地方自治体の棲み分けは、例として国際線ターミナル内を区切りとし、地方自治体では県境などが区切りとなる。検疫所は、当該疾患の疑い例に対して「体温測定を一日2回して、体調を検疫所に伝えるよう、また、具合が悪くなったら感染症専門の医療機関を受診する、保健所に相談する」と伝えるが、対象者がそうしなければならない法的な義務はなく、それらの事を、強制する力も国にはない。
また、地方自治体は国からの通知や事務連絡を受け取るが、それを現実的にどう適応させるかは、地方自治体ごとに違ってくる。今回の疑い例が国と地方をまたがったように、地方自治体をまたがることも十分想定されるので、地方自治体ごとのすり合わせをしっかりとしておかないと、実際に事が起こった時スムースに物事が進まなくなる可能性が高いと言える。
繰り返すが、国家の危機と判断された場合は、内閣危機管理監がリーダーとなって初動体制が敷かれる。総合調整として、各省庁に分担を振が、感染症の場合は、厚生労働省である。そうなると、平時の場合と同様のルート、すなわち、国内に入れないような水際作戦に過度に注力し、国内に関しては地方自体に依存するところが大きいという、平時の体制とほぼ変わらないやり方で、対応が進んでゆくことになる。
クリントン政権時代、初代FEMA長官を務めたジェームズ・ウイット氏は、講演で、「日本して、多くの異なる省庁が異なる責任をもっているようである(中略)どこが総括的な計画をもっているのか、どうやって一緒に協力していくか、どうやって資源を調節するのか。中央のレベルから実際の地方のレベルまでどのように協力し、どうやって一定の資源から最大の効果を引き出すのか。資源は限定されており、いかにむだを省くかなど計画はあるのかがはっきりしない」としています。様々な通知などは発令されていても、天然痘やエボラ感染症を受け入れられる医療機関は全国45で、総ベッド数80であり、医療スタッフも不足している現状は、ウィット氏の指摘がそのまま当てはまることを示す例だといえる
検疫法ができたのは昭和初期で、船が輸送の中心であった時代であり、現代にはそぐわない法律である。また、検疫法には「隔離・停留」という言葉が何度も使わる。隔離という言葉は、日本語ではあまり正確に区別されていないが、isolation=患者を一般集団から離す、quarantine=患者だけでなく、感染の可能性がある場合も一般集団から離す、という明確な区別がされている。特に患者でない人を一般集団から離す場合は、健常人である可能性もある人の行動制限を行うことから、十分な注意が必要なのは言うまでもない。
隔離することの効果(医学科学的でなく社会的、政治的な側面も含めて)が、個人の自由を制限することによって生じる負のインパクト、例えば倫理的な側面など、を上回った時にだけ、その権力を行使すべき、と、D.A. Henderson氏は、述べている(Bioterrorism JAMA books)。感染症が今後大きな社会問題となってゆく中で、隔離・停留の法的議論がなされないことは、エボラウイルス流行の際、その感染の可能性が否定できない米国の看護師が、個人の自由の主張を行い、州政府と争った状況とはあまりにかけ離れていると言える。
我が国の危機管理体制を、感染症対策を例に論じたが、「有事と平時の区別がついていない」という状況は、国家の安全保障上きわめて大きな問題である。早急な対策(法改正を含め)が求められる。