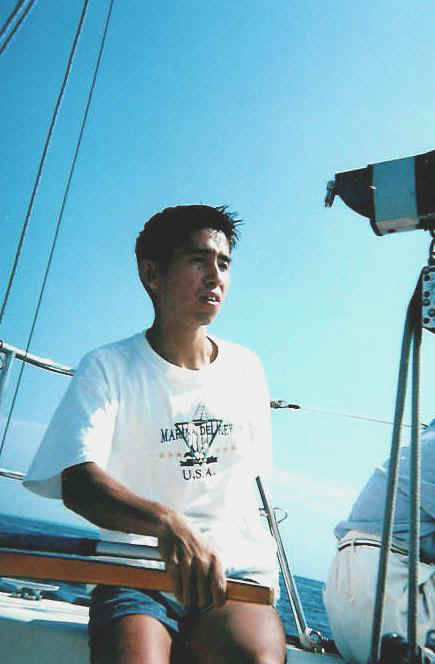右脳インタビュー ニコラス・E・ベネシュ
| 第92回 『 右脳インタビュー 』 (2013/7/1)
ニコラス・E・ベネシュ (Nicholas E. Benes) さん 公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)代表理事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
インタビュー後記 ベネシュさんはUCLAのMBAコースの時、William G. Ouchi教授の下で学んだそうです。当時、ハーバード大学のEzra F. Vogel博士が記した「Japan as Number One」(1979年)、ハーバード・ビジネス・スクールのRichard T. Pascale教授の「The Art of Japanese Management」(1981年)、そしてOuchi教授の「Theory Z」(1981年)の3冊の日本を称賛する本が脚光を浴びていました。 聞き手
1970年 長崎県生まれ。東京大学工学部卒、大学院修士課程修了。博士課程に在学中、アメリカズカップ・ニッポンチャレンジチームのプロジェクトへの参加を経て、海を愛する夢多き起業家や企業買収家と出会い、その大航海魂に魅せられ起業家を志し、知財問屋 片岡秀太郎商店を設立。クライシス・マネジメントとメディアに特化したアドバイザリー事業を展開 |
| 脚注 | |
| 注1 | |
| 注2 | |
| 注3 | |
| 注4 | |
| 注5 | |
| (リンクは2013年6月30日現在) |

 米国スタンフォード大学政治学学士号取得後、米国カリフォルニア大学(UCLA)で法律博士号・経営学修士号を取得。旧J.P.モルガンにて11年間勤務。米国カリフォルニア州及びニューヨーク州における弁護士資格、ロンドンと東京で証券外務員資格取得。現在、在日米国商工会議所(ACCJ)の成長戦略タスクフォース座長と人的資本タスクフォースの座長補佐を務める。2010年には、法務省と法制審議会会社法部会に対し会社法改正に対して意見を提供した金融庁主催コーポレートガバナンス連絡会議に所属する。これまでに在日米国商工会議所理事、同対日直接投資タスクフォース座長、内閣府対日直接投資会議専門部会の外国人特別委員、株式会社アルプスの取締役、スキャンダル後の株式会社LDH(旧名ライブドア)、株式会社セシールの社外取締役等を歴任した。
米国スタンフォード大学政治学学士号取得後、米国カリフォルニア大学(UCLA)で法律博士号・経営学修士号を取得。旧J.P.モルガンにて11年間勤務。米国カリフォルニア州及びニューヨーク州における弁護士資格、ロンドンと東京で証券外務員資格取得。現在、在日米国商工会議所(ACCJ)の成長戦略タスクフォース座長と人的資本タスクフォースの座長補佐を務める。2010年には、法務省と法制審議会会社法部会に対し会社法改正に対して意見を提供した金融庁主催コーポレートガバナンス連絡会議に所属する。これまでに在日米国商工会議所理事、同対日直接投資タスクフォース座長、内閣府対日直接投資会議専門部会の外国人特別委員、株式会社アルプスの取締役、スキャンダル後の株式会社LDH(旧名ライブドア)、株式会社セシールの社外取締役等を歴任した。